メンタリストDaiGoさんの著書『知識を操る超読書術』は、私たちが普段何気なく行っている「読書」の常識を覆し、得た知識を最大限に活用するための具体的な方法を教えてくれます。単に速く読むだけでなく、いかに効率的に知識を吸収し、アウトプットに繋げるか。この問いへの答えが、本書には詰まっています。今回は、特に重要だと感じたポイントをいくつかピックアップしてご紹介します。
読書前の「準備」が成功を左右する
DaiGoさんは、読書から得られる知識のアウトプットは、なんと「本を読む準備」ができているかどうかで7割決まると断言しています。多くの人が準備の重要性を知らないため、これが大きな差を生むと言います。
まず、本を読む前に以下の3つの質問を自分に問いかけることが重要です。
「なぜ、この本を読もうと思ったのか?」 「この本から何を得たいのか?」 「読んだ後、どういう状態になりたいと願っているのか?」
引用:『知識を操る超読書術』メンタリストDaiGo著
これらの問いかけは、脳の好奇心を刺激し、記憶の定着率を高める効果があるとのこと。質問と答えを聞いて脳の好奇心を司るエリアが活性化した被験者は、そうでない被験者と比べて記憶率が大きく向上したという研究結果も示されています。
速読と熟読の賢い使い分け
スキミングで効率的に読むべき箇所を見極める
1冊の中の重要な箇所とそうでない箇所を判別するために速く読み、重要なところは何度も熟読しましょう。
引用:『知識を操る超読書術』メンタリストDaiGo著
DaiGoさんは、すべてのページを均等に読むのではなく、「スキミング(拾い読み)」の重要性を説いています。これにより、読むべき部分と読み飛ばしても良い部分を見極め、効率的に読書を進めることができます。
■ その本の分野の「基礎知識」をしっかり頭に入れること ■ スキミング(拾い読み) によって、読み飛ばす部分を決める、すなわち集中的に読む本や読むべき箇所を決める
引用:『知識を操る超読書術』メンタリストDaiGo著
研究データによると、読み手の頭に基礎知識があり、ある程度読み慣れたジャンルの本であれば、精読するべき場所は1冊につき7%から11%程度しかないそうです。すべてのページを隅々まで読む必要はない、という発想の転換が大切です。
導入と結論に注目する
本の概要や概論を知りたい場合は、「導入と結論」を読むだけで要点をつかむことができます。特に結論部分は、「しかし」や「つまり」といった接続詞の後に著者が伝えたいメッセージが書かれていることが多いとのことです。
読書中の工夫で記憶を最大化
メモを取りながら読む
DaiGoさんは、読む前、読んでいる最中、読んだ後にメモを取ることを習慣にしているそうです。
本に書かれている内容は要するに何なのか、何に使えるのか。根拠となる出典はあるのかなど、読み進めながらその都度、思いついたり考えたりしたことをメモにしてまとめています。 この読み方で、私は知識の最大化を実現しています。
引用:『知識を操る超読書術』メンタリストDaiGo著
これは、読んだ内容を自分事として捉え、具体的な行動に結びつけるための重要なプロセスと言えるでしょう。
予測読みとつなげ読みで理解度を深める
-
予測読み: 読み始める前に内容を予測し、読み終わった後に実際の情報と比較することで、理解度を高めます。
-
つなげ読み: 本を読みながら、自分の知識、体験、世の中の出来事の3つを結びつけていくことで、新たな洞察を生み出します。
効率的な知識定着のためのアウトプットと復習
「教えるつもり」で読む
ワシントン大学の実験によると、実際に人に教えたかどうかは重要ではなく「教えるつもりで読む」だけで記憶への定着率が 28%上がることが判明しています。アウトプットを想定しない読書は、自分はわかっていると思い込んでいるに過ぎません。
引用:『知識を操る超読書術』メンタリストDaiGo著
読んだ内容を誰かに説明することを意識すると、より深く理解しようと努めるため、記憶に残りやすくなります。かのアルベルト・アインシュタインも「6歳の子どもに説明ができなければ、理解したとは言えない」と語っているように、「伝える」という意識が知識の定着に不可欠です。
最適な復習タイミングと睡眠の活用
復習のベストなタイミングは**「忘れた頃に復習すること」**です。また、読書と読書の間に短時間の睡眠を挟む「インターリーピング睡眠」は、記憶力と想起能力を約2倍向上させるとのことです。
「疲れを感じたら切り上げ、眠る。起きてから続きを読み始める」
引用:『知識を操る超読書術』メンタリストDaiGo著
読書効率を高める身体的なアプローチ
運動と読書
イリノイ大学の研究により、20分間の軽いウォーキングが脳の活動を向上させることが分かっています。やる気が出ない時や集中したい時に、散歩などの軽い運動を取り入れるのは非常に効果的です。
運動後4時間が1日のうち最も集中力の高い時間帯になるので、その間に1冊5分ペースで「スキミング」し、かなりの量の読書をし、これはという本があればじっくり読み込んでいきます。
引用:『知識を操る超読書術』メンタリストDaiGo著
本の選び方と情報の取捨選択
エビデンスの重要性
DaiGoさんは、エビデンスのないノウハウやマニュアルが記載されている実用書は基本的に読む必要がないと述べています。情報の信頼性は、巻末の参考文献リストや著者のプロフィール、これまでの著作から推測できるとのことです。
また、
健康書で「極論」を述べる著者には、しばしば情報をフェアに見る能力が欠けている傾向があります。いわゆるポジショントークであり、自分にとって都合のいい情報しか選んでいないので、読んでいると「この本を実践しても効果は出ないのでは?」 という疑問が浮かびます。
引用:『知識を操る超読書術』メンタリストDaiGo著
と述べており、都合の良い情報しか選んでいない可能性があるため注意が必要です。
基本文献を読む
各分野の基本となる名著を読むことも推奨されています。
ビジネスの戦略なら、『孫子』
リーダーシップなら、『君主論』
経済学なら、『国富論』
自己啓発なら、『人を動かす』
心理学なら、『ヒルガードの心理学』
社会心理学なら、『影響力の武器』
行動経済学なら、『世界は感情で動く』
マネジメントなら、『マネジメント』
マーケティングなら、『ザ・コピーライティング』
交渉についてなら、『世界最強の交渉術』
顧客心理なら、『シュガーマンのマーケティング 30 の法則』
脳科学なら、『脳を鍛えるなら運動しかない!』
バイアスについてなら、『ファスト&スロー』
引用:『知識を操る超読書術』メンタリストDaiGo著
私も何冊か読んでみましたが、名著だけあって知見が広がります。
特に『シュガーマンのマーケティング 30 の法則』と『ファスト&スロー』はお気に入りです。
まとめ
『知識を操る超読書術』でDaiGoさんが伝えているのは、単なる速読テクニックではなく、いかにして本から最大限の知識を引き出し、それを自分の血肉とし、現実世界で活用していくかという、より本質的な読書術です。
これらの知見を参考に、ぜひあなたの読書習慣を見直してみてはいかがでしょうか。読書に対する意識が変われば、得られる知識の量と質も格段に向上するはずです。
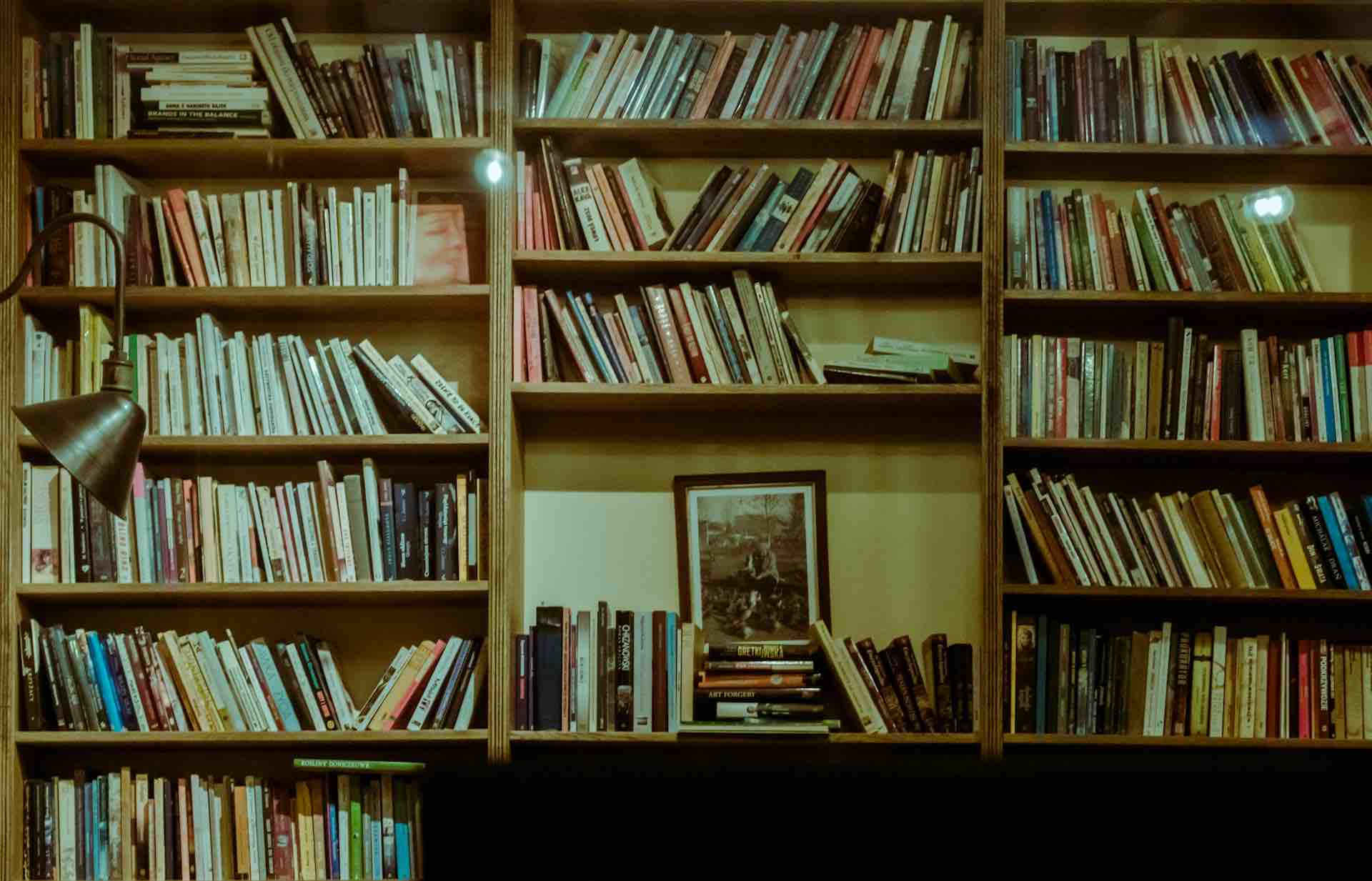
コメント