多くの人が「頭がよくなりたい」と思っていますが、いざ何をすればいいのかとなると、漠然としていてよくわからないものです。しかし、白取春彦氏の著書『頭がよくなる思考術』には、私たちが普段の生活の中で実践できる具体的なヒントが詰まっています。
この本は、単なる知識の詰め込みではなく、私たちがどう考え、どう生きるか、という根本的な部分に焦点を当てています。今回は、この本から得られる、思考をクリアにするための5つのポイントを、引用を交えながらご紹介します。
思考の道具は「言葉」である
私たちは普段、無意識に様々なことを考えていますが、その思考を支えているのが言葉です。著者は、言葉を使わなければ、私たちはきちんと考えることができないと指摘します。
わたしたちが考えるときに使う道具とは何だろうか。言葉である。人間は言葉を使ったときにだけ、ちゃんと考えることができるのだ。
引用:『頭がよくなる思考術 頭がよくなるシリーズ』白取春彦著
感情やイメージに流されるのではなく、言葉を使って論理的に思考を組み立てる。これが、質の高い思考の第一歩です。日々の出来事を言葉で表現してみたり、自分の考えを文章にしてみたりする習慣をつけることで、思考力は鍛えられます。
感情と好き嫌いから自分を切り離す
思考の妨げになる大きな要因の一つが、感情や好き嫌いです。著者は、多くの人が自分の好みや感情に従うことを「考えること」だと勘違いしていると述べています。
考えるときには、感情と好き嫌いを自分から離しておかなければならない。 しかし、多くの人は自分の好みと感情にしたがうことが考えることだと思っている。
引用:『頭がよくなる思考術 頭がよくなるシリーズ』白取春彦著
たとえば、誰かの意見を聞くときに「あの人は好きだから賛成」「この人のことは嫌いだから反対」と判断してしまうことはありませんか? これは思考ではなく、感情の反応です。客観的に物事を判断するためには、一度自分の感情を脇に置いて、冷静に事実に向き合う必要があります。
なぜ?どうして?と問いかける
ドイツに住んでいた経験から、著者は日本人とドイツ人の思考様式の違いとして、「なぜ?」と問うことの少なさを挙げています。
わたしはドイツに七年住んでいたが、もしドイツと日本はどこがもっとも違うかと問われたら、こう答える。ドイツ人は子供も大人も頻繁に「なぜ」と問いかけるが、日本では「なぜ」と問うことが極端に少ないばかりか、「なぜ」と問うこと自体が嫌われる、と。
引用:『頭がよくなる思考術 頭がよくなるシリーズ』白取春彦著
当たり前だと思っていること、決められていることに対して「なぜ?」と問いかけることは、新しい発見やより良い解決策を生むきっかけになります。子供のような素直な好奇心を持つことが、思考を深める鍵となるでしょう。
「心配」の正体は「妄想」だと知る
将来への不安や、漠然とした心配で頭がいっぱいになることはありませんか? 著者は、その**「心配」の多くが「妄想」に過ぎない**と断言します。
あなたは「心配している」と言う。けれども、あなたの心配の中身は妄想である。 妄想はあなたの心身を傷つけ、妄想を口に出せば、あなたは相手から軽蔑されるだろう。
引用:『頭がよくなる思考術 頭がよくなるシリーズ』白取春彦著
心配のほとんどは、実際に起こるかどうかわからない、自分の頭の中で作り出した想像です。こうした無意味な妄想は、私たちのエネルギーを奪い、行動を鈍らせます。心配事があるときは、「これは事実か?それとも妄想か?」と自分に問いかけてみましょう。事実ではないと気づけば、余計な不安から解放され、より建設的な思考に集中できます。
問題を「教え」として捉える
人生には、どうしても解決できないような、面倒でくだらないと思える問題が起こることがあります。しかし著者は、その問題の中にこそ、貴重な「教え」が隠されていると語ります。
問題の中にそのような教えを見出すことができれば、問題は一変して尊いものとなる。自分の人生に必要なものとなる。
引用:『頭がよくなる思考術 頭がよくなるシリーズ』白取春彦著
困難な問題に直面したとき、「どうしてこんな目に遭うんだ」と嘆くのではなく、「この問題は自分に何を教えてくれているのだろうか?」と考えてみる。そうすることで、一見ネガティブな出来事が、自己成長のための大切な機会に変わるのです。
まとめ
『頭がよくなる思考術』は、思考は訓練によって磨かれるものだと教えてくれます。感情に流されず、素直に「なぜ?」と問いかけ、無駄な心配から自分を解放する。そして、目の前の問題を成長の機会として捉える。
こうした日々の意識が、私たちの思考をより豊かにし、人生をより良く導いてくれるはずです。ぜひ本書を手に取って、あなた自身の「思考術」を磨いてみてください。
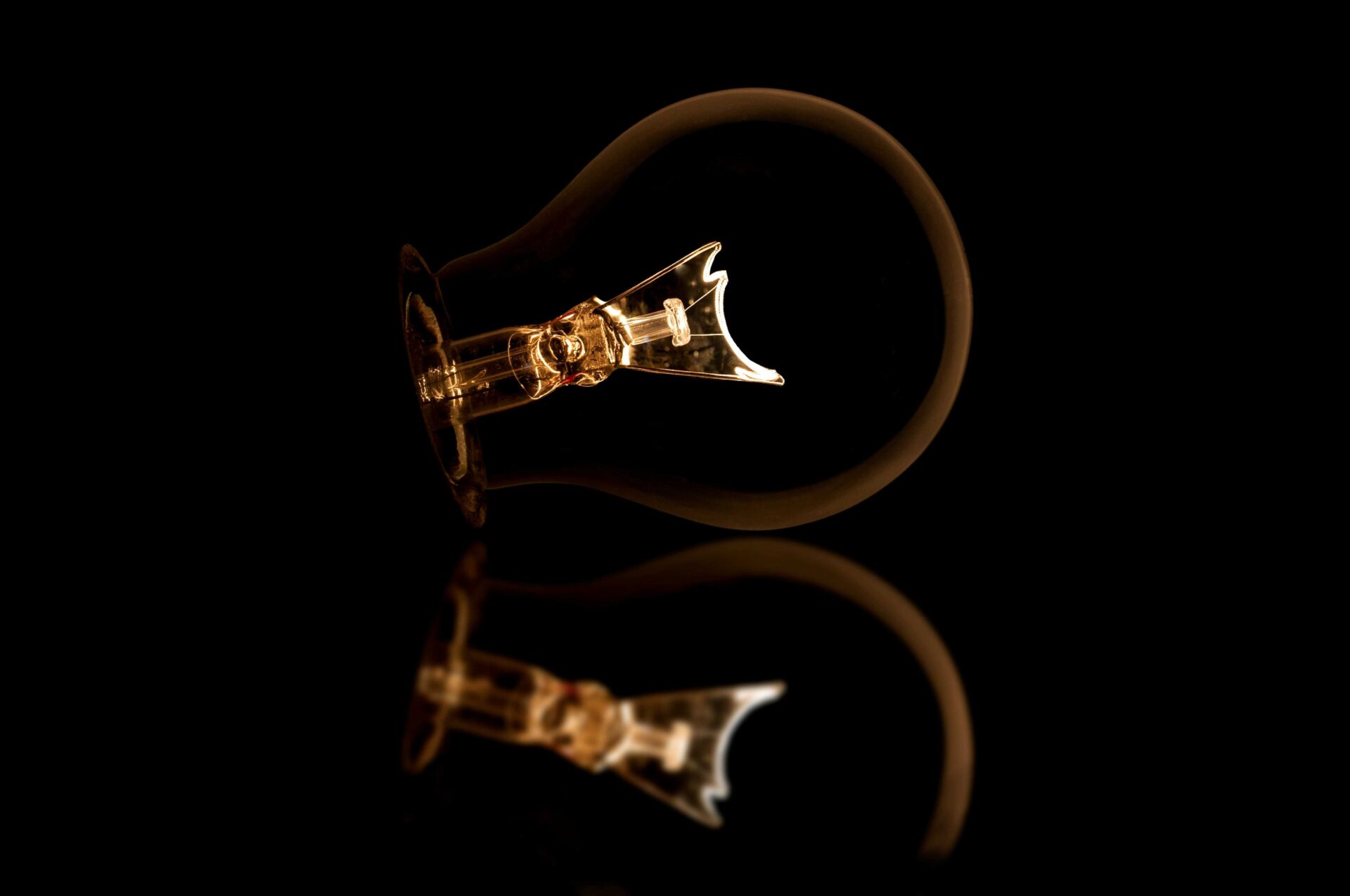
コメント