普段の会話で、ちょっと気の利いた悪口を言ってみたいと思ったことはありませんか?ただし、ただの悪口では面白くありません。本当に面白い悪口とは、知的なひねりが効いていて、聞いた人が思わず「なるほど!」と唸ってしまうようなもの。堀元見さんの『教養(インテリ)悪口本』は、そんな「面白い悪口」の宝庫です。
「つまらない悪口」と「面白い悪口」
世の中には悪口が溢れていますが、そのほとんどは単なる悪口で、聞いていて何の面白みもありません。しかし、著者はこう指摘します。
だけど、それは悪口がつまらないのではなく、「つまらない悪口」なのである。ここを履き違えてはいけない。世の中には「面白い悪口」も存在する。
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
まさにその通り!本書は、歴史、科学、哲学など、多岐にわたる教養を背景にした、聞いている方も楽しくなるような「インテリ悪口」を紹介してくれます。
知的に人を評する悪口
本書には、相手の行動や性質を鋭く、そして教養をもって指摘する悪口の例が満載です。
「何の役にも立たない」を遠回しに言う
植物学の分野で最も研究が進んでいるとされるシロイヌナズナ。しかし、その実用性は意外なほど低いそうです。
そんなシロイヌナズナは、人間にとってなんの役にも立たない植物である。食べられないし、薬にもならないし、利用価値がまったくない。
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
これを踏まえて、「何の役にも立たない」ことを遠回しに言いたいときに「シロイヌナズナみたいだね」と表現する、といった具合です。知的な人ほど、この比喩の面白さに気づくでしょう。
思考停止な人への悪口
「証明されてない勝手な前提を置いて進められる論証」を指す論理学の詭弁に「先決問題要求の虚偽」という言葉があります。
「先決問題要求の虚偽」は、論理学における詭弁の一種。 証明されてない勝手な前提をおいて進められる論証のことである。
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
例えば、以下のような会話で使えます。
「えっ、あの面白さ分かんないの? センスなくない?」 「それは先決問題要求の虚偽だよ。え? もしかして進化論信じてないの?」
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
相手の思考の甘さを指摘するだけでなく、さらに一歩踏み込んで、教養の有無にまで言及するパンチの効いた悪口です。
歴史や科学から学ぶ悪口
歴史上の出来事や科学的事実から着想を得た悪口も、本書の醍醐味です。
消極的な戦略が大失敗した人へ
古代ギリシアのアテナイの指導者ペリクレスは、戦争中に「とにかく守る」という消極的な戦略を取り、結果的に大失敗に終わりました。
この戦争でペリクレスは、「とにかく守ろう」という方針を打ち出した。「城壁の中にこもって守っていれば相手は諦めるに違いない」みたいな感じ。 とにかく消極的な戦略である。 しかし、結果から言えば、この戦略は大失敗だった。
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
この歴史的背景を知っていれば、例えば「ペリクレスばりの戦略だな」と皮肉ることで、相手の消極策がいかに愚かであるかを、遠回しに伝えることができます。
余裕ぶっこいて失敗した人へ
フランス革命期に国王ルイ16世と王妃マリー・アントワネットが起こした「ヴァレンヌ逃亡事件」は、逃亡中に余裕をぶっこいた行動のせいで失敗に終わりました。
ルイ 16 世とマリー・アントワネットは、 明らかに急がなきゃいけない逃走劇なのになぜか余裕ぶっこいた行動 を取って失敗してしまった。これがヴァレンヌ逃亡事件の面白さである。
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
「ヴァレンヌ逃亡事件のルイ16世かよ!」とでも言えば、相手の詰めの甘さをユーモラスに指摘できます。
「まさかそんなにひどいとは」という品質へ
「パリティビット」という、データ転送の誤りを検出する仕組みがあります。しかし、あまりにも間違いが多いと、このパリティビットも意味をなさなくなります。
しかし、 想定を超えてありえないぐらい間違われてしまうと、意味をなさなくなる。 したがって、「どんだけ間違うんだよ⁉」とか「想定を超えた低品質だよ‼」とか言いたくなった時には、「パリティビットが意味をなさない品質」という表現が使える。
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
とんでもない低品質に対して、「パリティビットが意味をなさない品質だね」と言えば、そのひどさを最大限に表現できるでしょう。
日常で使える(?)インテリ悪口
本書には、日常生活の様々な場面で使える悪口も紹介されています。
褒められたくない時の悪口
二日酔いの時、私たちはつい自分を責めてしまいがちです。しかし、著者はこんなライフハックを提案しています。
僕ぐらい開き直る名人になると アセトアルデヒドを責める。 「なんであんなに飲んじゃったんだろう……」と後悔していると気分が落ち込むばかりだが、「 アセトアルデヒドふざけんな‼」と考えると闘争心が湧いてくる。二日酔いの時にオススメのライフハックだ。
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
これは悪口というよりも、前向きな捉え方の提案ですね。自分を責める代わりに、原因となる物質を悪者にする、というのは面白い発想です。
金遣いが荒い人への悪口
明治の政治家、黒田清隆は、酒癖が悪く、公衆の面前で泥酔して問題を起こすことが多かったそうです。そんな逸話から、こんな悪口が生まれます。
「マジかよ。 黒田清隆ばりだな」
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
破天荒な振る舞いをされた時に、この一言で場を和ませつつ、相手にクスリとさせるようなパンチを効かせられます。
道徳的ぶる人への悪口
常に理性的に振る舞っているように見える人でも、家では意外な一面を見せることがあるかもしれません。
常に理性的な振る舞いをしている人は 外で道徳貯金を使い果たしているので、家の中ではとんでもない暴れん坊 ということになる。 したがって、「いつもキレイゴトばかり言ってる人」「品行方正な人」にはこの悪口が使える。「道徳貯金が赤字じゃない? 家で人種差別とかしてる?」
引用:『教養(インテリ)悪口本』 堀元 見著
これはかなり攻めた悪口ですが、相手の建前と本音のギャップを突く鋭い一言です。
ユーモアと知性で会話を豊かに
堀元見さんの『教養(インテリ)悪口本』は、単に人を貶めるための悪口ではなく、ユーモアと知性を兼ね備えた「面白い悪口」の可能性を示してくれます。本書を読めば、あなたの会話に深みと面白さが加わること間違いなしです。
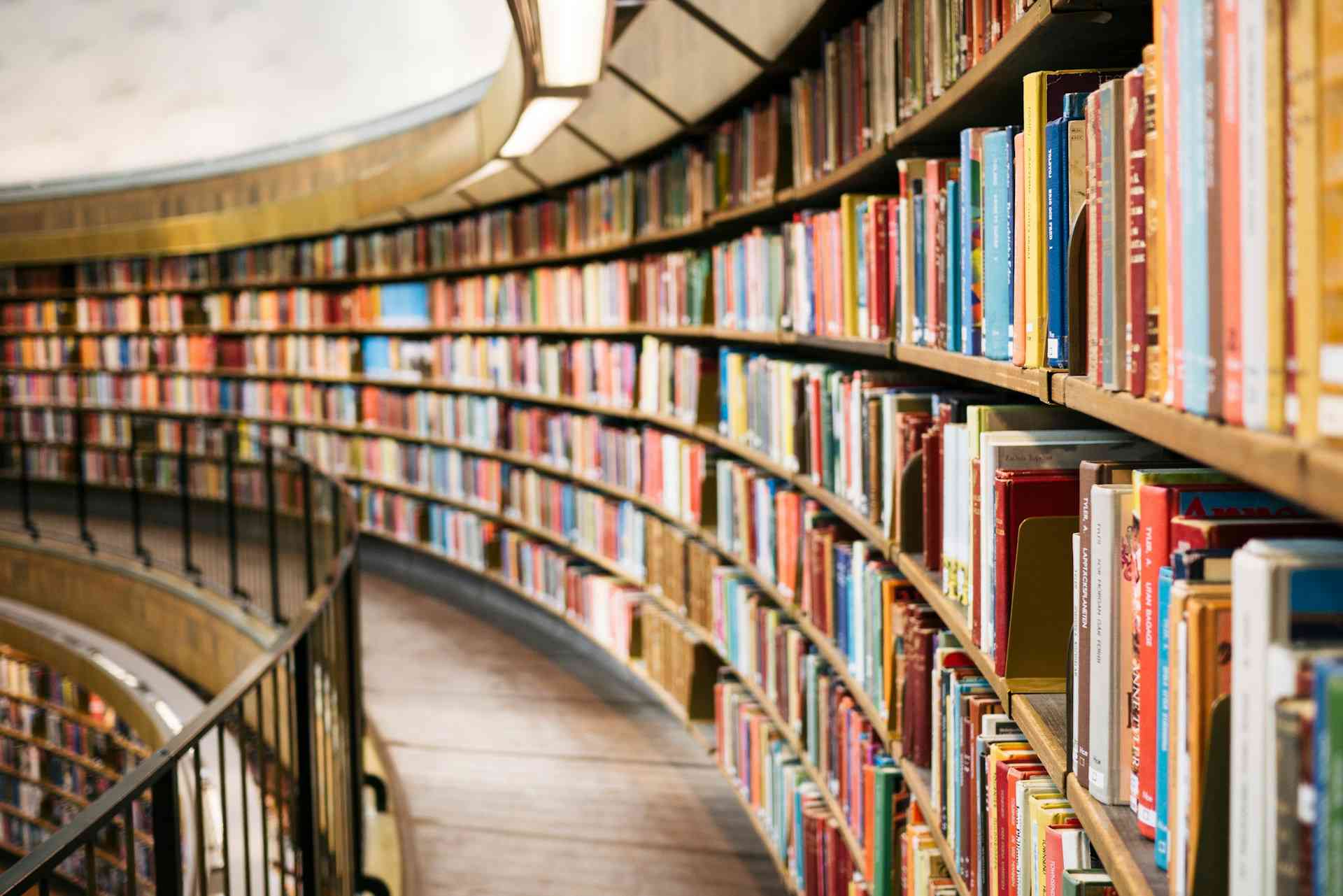
コメント