近年、めざましい進化を遂げる生成AI。私たちの仕事や生活にどのような影響をもたらすのでしょうか?今回は、今井翔太氏の著書『生成AIで世界はこう変わる (SB新書)』から、注目のポイントをいくつかご紹介します。
ChatGPTの仕組みと驚異的な能力
「ChatGPT」という言葉を耳にする機会が増えましたが、具体的にどのようにしてあの高度な会話能力が実現されているのでしょうか?
「ChatGPTは『穴埋め問題の学習』『教師ありファインチューニング』『人間からのフィードバックに基づく強化学習』を大規模に行うことによって実現されたのです。」
引用:『生成AIで世界はこう変わる (SB新書)』今井 翔太著
これは、大量のテキストデータから次の単語を予測する「穴埋め問題」を繰り返し学習し、さらに人間が適切な応答を教え込み、最終的には人間からのフィードバックに基づいてより良い回答を生成するように学習するという、多段階のプロセスを経て開発されたことを示しています。この複雑な学習プロセスが、ChatGPTの驚くべき能力の根源にあるのです。
AIがもたらす労働の変化:高スキル職ほど影響大?
生成AIの進化は、私たちの仕事に大きな影響を与えると言われています。特に興味深いのは、その影響が及ぶ範囲についてです。
「高学歴で高いスキルを身につけた者が就くような賃金が高い職業であるほど、生成AIによる自動化の影響を受ける可能性が高い。ただし、本当に習得に時間がかかる高度なスキルが必要とされる職業に関してはその限りではない」
引用:『生成AIで世界はこう変わる (SB新書)』今井 翔太著
これは一見すると逆説的ですが、ルーティン化された高スキル業務はAIによる自動化の対象になりやすい一方で、真に「暗黙知」が求められるような、習得に膨大な時間を要する高度なスキルは、AIによる置き換えが難しいことを示唆しています。
ポランニーのパラドックスと「暗黙知」の重要性
ここで重要な概念として挙げられるのが、「ポランニーのパラドックス」です。
「『ポランニーのパラドックス』という有名な説があります。これは哲学者マイケル・ポランニーの言葉をもとに提唱されたもので、その内容は『人は言葉で表現できる以上のことを知っている』というものです。この『言葉で表現できる以上のこと』を『暗黙知』と言います。」
引用:『生成AIで世界はこう変わる (SB新書)』今井 翔太著
つまり、私たちが日常的に行っている多くの判断や行動は、言葉では説明しきれない「勘」や「経験」に基づいている部分が大きいということです。この「暗黙知」こそが、AIによる労働の置き換えが進む中で、人間が強みを発揮できる領域となるでしょう。
「労働補完型」と「労働置換型」:AI活用の視点
生成AIが労働に与える影響を考える上で、その技術がどのような性質を持つのかを理解することは非常に重要です。
「生成AIなどの技術による労働への影響を考える場合、その技術が『労働補完型』の技術なのか、『労働置換型』の技術なのか、分けて考える必要があります。労働補完型の技術とは、人間の労働を補助し、その労働自体を楽にしたり、生産性を上げたり、新しい仕事を生み出すきっかけになるような技術です。一方の労働置換型の技術とは、文字通り人間の労働を完全に置き換え、人間が介在する余地をなくしてしまうような技術です。」
引用:『生成AIで世界はこう変わる (SB新書)』今井 翔太著
私たちは生成AIを「労働補完型」として捉え、いかに人間の創造性や生産性を高めるツールとして活用できるかを考えるべきでしょう。
Copilotが示す生産性向上:プログラミングの事例
実際に、生成AIが人間の生産性を飛躍的に向上させた事例も存在します。
「GitHubがMicrosoft社やMITと共同で行った研究では、開発者をCopilotを使う/使わないの2つのグループに分け、あるプログラミング言語を使ってサーバープログラムを開発するというタスクを行わせました。この結果、Copilotを使わなかったグループの開発者が平均161分でタスクを完了させていたのに対し、Copilotを使ったユーザーはその半分以下の平均 71 分でタスクを完了させたという結果が出ています。つまりCopilotを使うことで、生産性が2倍以上アップしていることになります。」
引用:『生成AIで世界はこう変わる (SB新書)』今井 翔太著
この事例は、生成AIが特定のタスクにおいて、人間の作業効率を大幅に向上させる可能性を明確に示しています。プログラミングのような複雑な作業においても、AIが強力な「労働補完型」ツールとして機能することが証明されたと言えるでしょう。
AI時代を生き抜くために:努力とタイミング
生成AIの進化が加速する現代において、私たちがどのようにスキルを磨き、キャリアを築いていくべきなのでしょうか。著者は、普遍的な成功の秘訣を説いています。
「勝負に勝つには、人ができない努力を淡々とやり続けたり、勝負どころを見極めて『ここだ』と思ったら一気に仕掛けたりすることが必要です。それはゲームに限らず、物事に勝つための普遍的なやり方だと思います。たとえば『研究者として活躍したい』と思うなら、人と違うような極端なことをやらないと勝てない。ですから、私も博士時代にはひたすら論文を読み、文献を読み、論文を書きまくるという、すごく極端な戦略を取っていました。あとはタイミングですね。ここだと思ったら一気にいく。それ以外のときは地道に淡々とやる。そうしたメリハリは必要でしょう。」
引用:『生成AIで世界はこう変わる (SB新書)』今井 翔太著
これは、AIがどれだけ進化しても、最終的には個人の「努力」と「タイミング」が重要であることを示唆しています。AIに代替されにくい領域、つまり「暗黙知」を必要とするような高度なスキルを習得するために、人とは異なる極端な努力を継続すること。そして、チャンスを逃さずに一気に仕掛ける「ここだ」というタイミングを見極めること。これらが、AI時代を賢く生き抜くための鍵となるでしょう。
生成AIは、私たちの社会に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。その進化の方向性や、私たちに求められる対応について、皆さんはどのように考えますか?
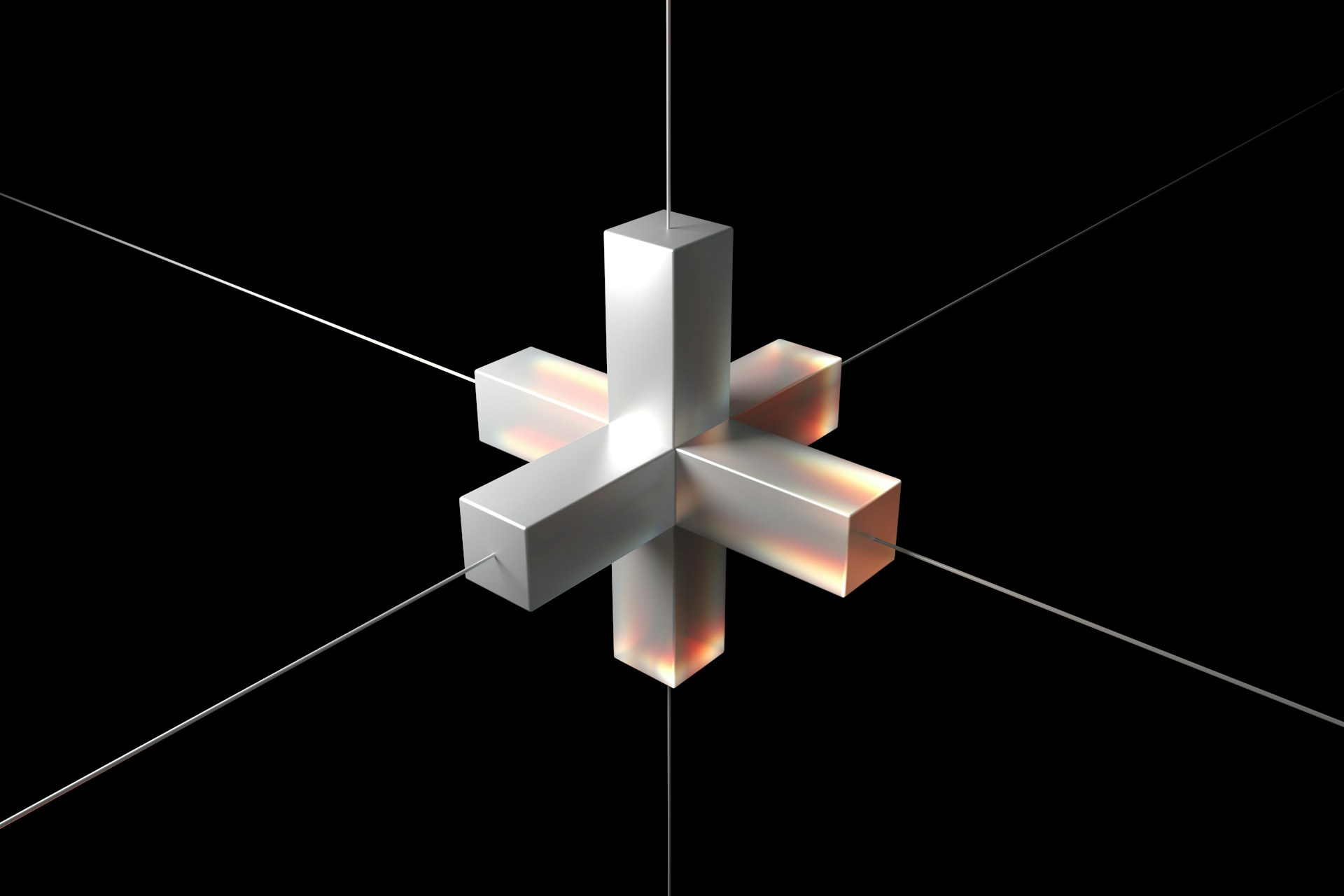
コメント