顧客対応の現場で避けて通れないのが、クレームやカスタマーハラスメントです。どのように対応すれば良いのか、頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。今回は、加藤義樹氏の著書『カスタマーハラスメント撃退の教科書』から、その心得と具体的な対応策を学び、皆さんの日々の業務に役立つヒントをお届けします。
クレームは「なくならないもの」と覚悟する
私たちは、どんなに努力してもミスをなくすことはできません。技術が進歩しても、エラーやバグ、故障はつきものです。そして、クレームの多くはそうしたことから発生します。
どれだけスキルを上げても人間のやることにミスやうっかりなど、そしてどれだけ技術が進んでもエラーやバグ、故障などは付きものだからです。クレームはそういったことから起こることが多いのです。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
さらに、こちら側がレベルアップしても、クレームもそれに合わせて「レベルアップ」するか、あるいは「まったく新しいタイプ」のクレームが発生するといいます。
クレームをなくそうとしてスタッフさんのスキルを上げたり先進的なシステムを導入したりと、『こちら側のレベルアップ』をすると、それに合わせたかのように『クレームもレベルアップ』するか、もしくはそれまではなかったような『まったく新しいタイプのクレーム』が発生するからです。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
だからこそ、一番大切なのは「クレーム・トラブルは起こるものだと覚悟を決める」ことだと著者は説きます。
ズバリ『クレーム・トラブルは起こるものだと覚悟を決める』、つまり『腹を括る』ということです。人間は予想外・想定外の出来事が起こると、頭がフリーズ(思考停止)したり、パニックに陥ってしまうことが多いです。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
悪質なクレームへの具体的な対応ステップ
クレームの中には、悪意のあるものや、度を超えた言動を伴うものも存在します。そのような場合にどう対応すべきか、具体的なステップが示されています。
相手を「プロファイリング」する
まずは相手の言動から心理状態や性格を推測する「プロファイリング」が重要です。
相手の表情、目線、話し方、言葉のチョイスの仕方、間の取り方、しぐさなどから相手の心理状態や、性格などを推測、さらには着ている服や身に付けているものなどからも情報を得ようとする、私が『プロファイリング』 と呼んでいる方法です。私はこの『プロファイリング』はとても重要だと思っていて、そこから得られた情報から推測したり仮説を立てて、それをもとに対応方法や改善・解決方法を考えて組み立てていく、というやり方が得意でもあります。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
このプロファイリングによって得られた情報をもとに、対応方法を組み立てていきます。
情報の確認を怠らない
お客様の言い分が常識外れだと感じても、まずは事実確認を徹底することが大切です。
「購入後いつでも交換可能と言われた」といった、それはあり得ないだろうと思う場合でも、『誰に言われたのか?』『どういう言い方をされたのか??などの確認は必要です。意外にありがちなのが、「Bさんという名前のスタッフさんだった」と言われた場合に、「あ……Bさんなら間違った案内・曖昧な言い方をすることはあるかも(過去にもあったし)」といったこともあり得ますので、やはりできる限りお客さまの言い分については内容の確認をしたほうがよいですね。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
また、責任者として対応を代わる際も、まずは相手の言い分を確認することから始めます。
まずお客さまにご挨拶をした後、「ただ今スタッフからの報告で〇〇というようにお伺いしましたが、お間違いないでしょうか?」や、「〇〇というようにお伺いしましたが、間違いがあってはいけませんので、念のためよろしければもう一度お客さまから詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?」と聞きます。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
悪意あるクレームへの「反撃・撃退モード」
悪意のあるクレームに対しては、毅然とした態度で臨む必要があります。
共通しているのは、悪意のない場合は、通常通り丁寧な対応を心がければよほどのことがない限りそれ以上揉めることはないと思いますが、問題は悪意があるパターンで、 責任者として『店頭(現場)の状況把握を迅速に』、そして『臆せずビビらず冷静に』 ということです。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
そして、度を越した、一線を越えたと判断した場合は、「お客さまではなくなった」と判断し、迅速に「反撃・撃退モード」に切り替えるべきだと著者は述べています。
度を越した・一線を越えたと判断したら、その瞬間『お客さまではなくなった』 と判断=クレーマー 判定 し、迅速に『反撃・撃退モード』 のスイッチを入れなければならない、というのが私の考えです。引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
具体的には、以下のようなステップを踏みます。
-
お願いベースでの注意 まずは丁寧にお願いの形で注意を促します。
店長は ①「大変恐れ入りますが、他のお客さまのご迷惑にもなりますので、どうかお声をもう少し落としていただけないでしょうか?」とまずは『お願い』 ベースでお伝えします。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
-
予告 それでも収まらない場合は、対応を終了する可能性を伝えます。
②「お客さま、私としても解決を望んでおります。そのためにお互いに冷静に話し合いをさせていただきたいと存じます。しかし、これ以上大きなお声を出し続けられますと、冷静な話し合いができないばかりか、店舗の営業にも支障が生じますので、 大変不本意ではございますが、ご対応を終了とさせていただき、お引き取りいただく ことをお願いすることになってしまいます。お互いにとってそれは得策ではないと思いますが……」 などと『予告』 します。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
-
最終通告 それでも改善が見られない場合は、警察への通報も視野に入れた最終通告を行います。
③「先ほどからお願いしているように、冷静にお話しさせていただければと思うのですが……それが叶わないようでしたら、お引き取りいただくか、しかるべきところに通報せざるを得なくなるという判断に至ってしまうことになります」と、『最終通告(ファイナルアンサーの猶予)』 をします。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
躊躇せず110番通報を
警察への通報は躊躇する必要がないと著者は明言しています。
結局110番通報が一番早いと、実際に警察官に教えていただいたことがあります。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
特に、他のお客様やスタッフを威嚇するような言動があった場合は、すぐに判断すべきです。
他のお客さま・スタッフさんを威嚇するような態度・言葉が出た時
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
記録の重要性
万が一トラブルが大きくなり、弁護士の介入や裁判に発展した場合に備え、記録を残すことが極めて重要です。
万が一トラブルが大きくなって弁護士の介入や裁判などになってしまった時に、こうした『記録があるか・ないか』が結果に大きく影響することがあります。映像や音声はもちろんですが、たとえ『ただのメモ書き』でも、あるのとないのとでは弁護士や裁判官の印象・判断や結果が大きく変わることもよくあります。 こうなると、まさに『天国と地獄』ですね。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
ストレスマネジメントと自己肯定感
クレーム対応は大きなストレスを伴います。そのストレスとどう向き合うかについても言及されています。
ストレスは「感じるもの」と認識する
ストレスもクレームと同様に、ゼロにすることはできません。
ストレスというキーワードに対するポイントは、クレームと同様「ストレスを感じることは自然で当たり前のこと。ゼロにはできない」 と『認識=覚悟』することと、「ストレスはできる限り早く解放する」ということです。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
ストレスを軽減する工夫
著者は、ストレスを軽減するためのユニークな方法として、お客様を「お金さま」とイメージすることを提案しています。
もっと言うと、目の前のお客さまの「おでこに一万円札が貼り付いている」 ところをイメージします。そして心の中でこう唱えます。 「お客さまはお金さま」……これを3回唱えます(何回でもいいですが)。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
そして、クレーム対応を終えたら、自分を思い切り褒める「自画自賛」を推奨しています。
こんなメチャクチャなクレームの対応してるって、やっぱり私ってプロだわぁ~」と思いながら対応し、対応が終わったら「解決しちゃったよ~! 私最高!」「キレずに最後まで対応した私、お疲れ~!」「店長に交代せずに頑張れた!」「さすが私って店長だよね~♪」などと、文字通り『自画自賛』 するわけです。 そして「あぁ~これで今日もビールが美味しい!」までがセットです!(もちろんビールじゃなくてもOK)。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
継続的な学びと実践
クレーム対応スキルは一朝一夕には身につきません。継続的な研修と実践が不可欠です。
研修やセミナー、OJTなども 単発では効果はほとんどありません。定期的に実施して効果測定をしながら継続する、ということが重要です。実はこれは意外にも見落とされがちです。つまり 1回だけの研修で満足 してしまうことが多いのです。
引用:『カスタマーハラスメント撃退の教科書』加藤 義樹著
今回の記事が、皆さんのカスタマーハラスメント対応の一助となれば幸いです。クレームは避けられないものですが、適切な知識と心構え、そして具体的な対応策があれば、乗り越えることができます。
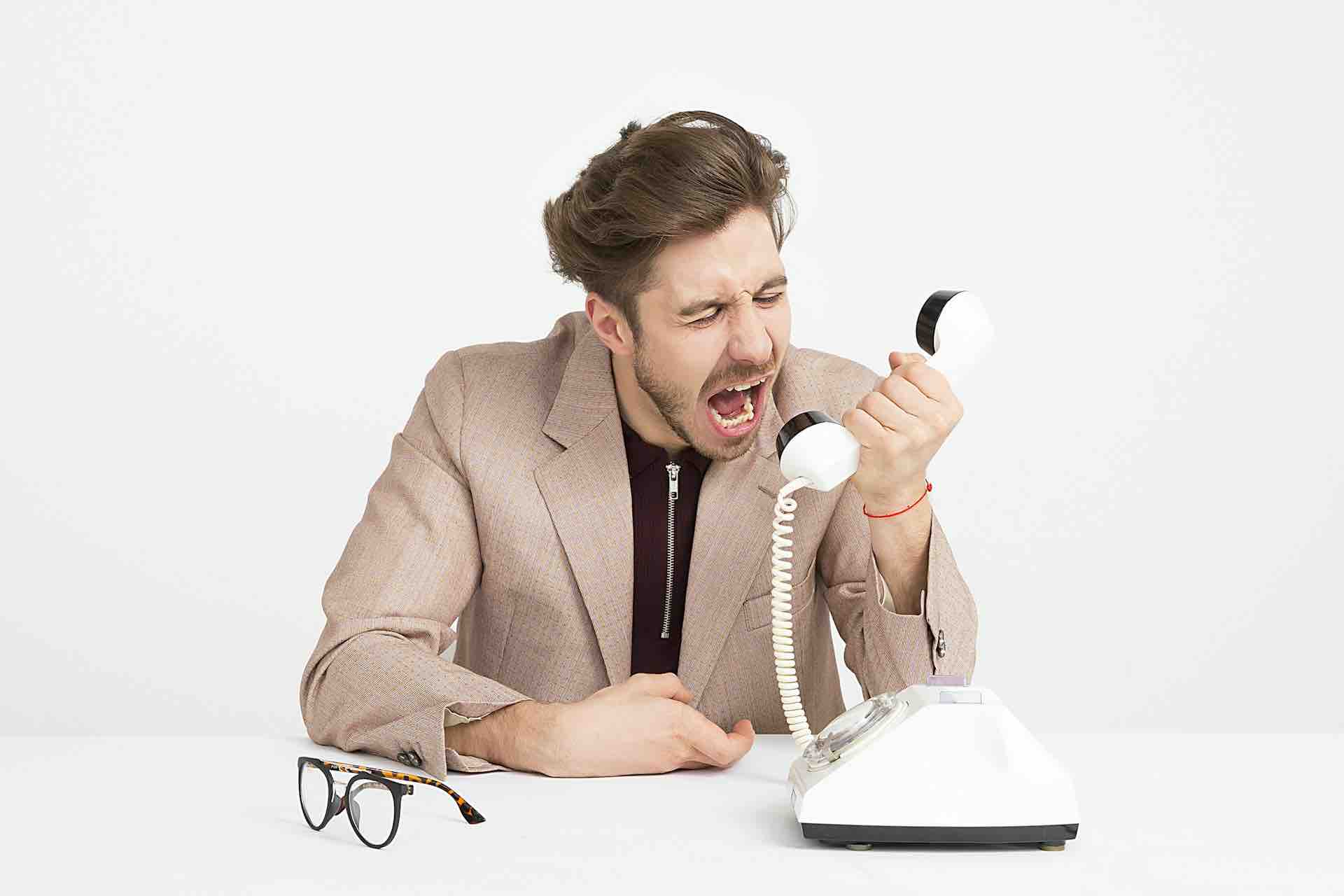
コメント