星野ロミ氏の著書『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』から、彼自身の言葉を通して、漫画村を巡る様々な側面、そして彼自身の思想と行動の原点に迫ります。法と感情の混同への警鐘、ITの世界で成功するための哲学、そして漫画村の技術的背景や彼が逮捕されるまでの経緯、さらには収監中の体験まで、彼のユニークな視点が語られています。
感情と法の分断
星野ロミ氏は、自身のサイトが漫画家や出版社に与えた損害を認識しつつも、感情に基づく世論や不正確な情報が法運用や裁判に影響を与えることへの強い懸念を示しています。
もちろんぼくのサイトによって、正当に得るべき利益が得られなかった漫画家さんや出版社の人たちは迷惑千万だったでしょう。感情として、それはよく理解できます。ただ、感情に基づく世論や誤った知識や恣意的な証拠の判定によって、法律が運用されたり裁判が行われたりすることは大問題ではないでしょうか。つまりそれは、やっていないことをやったことにされて罪に問われるという事態が、いつ誰の身にも、そう、あなたの身にも起こり得るからです。感情と法を混同してはいけないのです。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
この言葉は、法治国家における法の適正な運用がいかに重要であるかを訴えかけています。感情に流されることなく、客観的な事実と証拠に基づいて判断することの必要性を強調しているのです。
星野ロミを形作った哲学
彼のキャリアの出発点には、意外な側面があります。厚生労働省が定義する「ニート」の期間を経て、彼はITの世界での成功法則を見出していきます。
15 歳から 34 歳までの、家事・通学・就業をせず、求職活動もしていない独身者」というのが、厚生労働省のいう、いわゆる「ニート」の定義です。ぼくは高校を卒業したことにより、定義どおりのニートになりました。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
この経験が、彼にIT業界で生き抜くための重要な洞察を与えました。
ITの世界で勝負するのに決定的に意識しなければならないことは「自分にしかない強みを持つことと、参入障壁を作ること」だと気づき、その考え方を現在までずっと持ち続けています。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
さらに、彼は成功するための3つの原則を挙げています。
1つめは、ブルーオーシャン(成熟していない、開拓の余地がある業界のこと。対義語はレッドオーシャン) で勝負をすること。2つめは、自分にしかない強みを持つこと。3つめは、後発に抜かれないための参入障壁を作ること。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
これらの原則は、彼のビジネス戦略の根幹をなすものです。
漫画村の技術的側面と社会的反響
漫画村は、その技術的な仕組みにおいても注目されました。
ぼくはそれを避けるために、当時使い方としては目新しかった技術をメインとして使うことにしました。「リバースプロキシ」という技術です。できるだけ専門用語を使わずに簡単に解説しますと、「自分のサイトに画像を保存せず、アクセスのリクエストをそのまま元のサイトに返す」というシステムです。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
さらに、彼は漫画村の技術的な特徴を次のように説明しています。
もちろん細かいことを言うといろいろあるのですが、「漫画村のサイトには画像をアップロードせず、よそのサイトでアップロードされた画像に通り道だけを作る技術」とイメージしてください。URLは漫画村のURLになるのですが、実態として漫画村はただよそのサイトの画像を表示しているだけなのです。そして、第三者のサイトにアップされている画像が合法か違法かは、ぼくには判断しようがありません。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
漫画村は社会現象となり、そのアクセス数は驚異的でした。
漫画村は、その後2018年2月時点で、月に1億6000万のアクセスがあり、その 96%が日本からのトラフィックで、そのシェアは全Webサイトのうち 21 位である、と一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA) が発表したそうです(Yahoo!ニュースオリジナル特集「「漫画村」ブロッキング──誰が、どんな経緯で動いたのか」田中徹)。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
政府の対応も進み、ブロッキングの検討がなされました。
2018年3月 19 日午後、菅官房長官は「サイトブロッキングを含めあらゆる方策を検討している」と初めて公式に発言しました。4月 13 日には政府の知財戦略本部・犯罪対策閣僚会議は「ブロッキングを行うことが適当」という緊急対策を発表し、政府は「漫画村」「Anitube」「Miomio」の3サイトを名指しして、ブロッキングを行うよう事実上の実施要請。それを受けて、4月 23 日にNTTグループ4社は「準備が整い次第実施する」 旨 を発表します。ただし、これはのちの8月のことですが、3サイトのうち、少なくとも漫画村の閉鎖後、ブロッキングの実施は見送られることになります。NTTにはまだ良心があったのだと思います。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
逮捕、収監、そしてその後
海外での逮捕と収監の経緯についても、彼は詳細に語っています。複数の国籍を持つことが、彼の行動に影響を与えました。
本来、イミグレーション(出入国管理局) では、出国のスタンプがなければ入国できないはずです。が、レバノン・ブラジル・フランスの3ヶ国の国籍を持つ元・日産自動車会長カルロス・ゴーンもそうであったと言われる通り、複数のパスポートを持っている場合、出国のスタンプは入国の必要条件ではない、という国も多いのです。少なくともぼくは普通に入国できました。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
さらに、彼はイスラエルへの逃亡の可能性についても言及しています。
本当に捕まりたくなかったら、ぼくが持っている3つの国籍のひとつである、イスラエルに逃げたでしょう。なぜイスラエルなら本気で逃げたことになるのかの説明は難しいのですが、簡単に言えばイスラエルという国は、他国に自国民やユダヤ人を引き渡さない国なのです。少なくとも、他国から何か言われて、ハイハイわかりましたと素直に動く国でないことはたしかです。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
海外での拘束中、彼は驚くべき方法で情報にアクセスしていました。
その拘束中に、係員に 賄賂を払って、スマホを手に入れました。それで検索して、初めて自分が漫画村の件で拘束されているとわかったのです。「賄賂を払ってスマホを手に入れた」のくだり、初めて見た方はビックリするでしょうが、そんなに変わったことではありません。というのも、フィリピンの収容所は不法滞在者であふれかえっています。フィリピン側からすれば、不法滞在者がちゃんと罰金を払って自国に帰ってくれたら別にそれで困らないわけで、スマホを渡すぐらいはしないと連絡もできないだろう、ということです。フィリピンのほうがよほど人道的です。ぼくの周りのいろいろな国の収容者たちも、みんなスマホを持っていました。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
日本の刑務所内での体験も赤裸々に語られています。
日本の刑務所でTwitter、どうやって始めるんだとお思いでしょうが、国内の友人に140文字以内で手紙を書いて、代わりに書き込んでもらっていたというカラクリです。便箋1枚800字、1回に便箋が7枚まで使えるので、毎回全部使っていたわけではないですが、最大 40 ツイート分ぐらいは一度に送れました。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
そして、一審判決を受け入れた理由を、彼は次のように述べています。
一審判決を受け入れたその最大の理由。それは、檻の中に入っている時間を一番短くして、最短で戦闘態勢に戻ることができるのがその方法だったからです。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
司法制度への疑問と学び
日本の司法制度についても、彼は自身の見解を述べています。
日本の、特に普通の市民にとって、裁判所や検察といえば大変な権威があり、たしかな証拠をもとに適正な判断が行われる機関だ、という印象が強いかと思います。検察が起訴した事件については、その 99・9%が有罪になる、と言われていますが、これは日本では「それだけ検察はたしかな捜査をし、裁判所はそれを正しく裁いている」という文脈で語られることが多い気がします。
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
刑務所での読書は、彼に大きな影響を与えました。
刑務所の中で、ぼくはディズニーの元CEO、ロバート・アイガーの本を 貪るように読みました。その一節に大いに勇気づけられたので、ここに一節を引用します。「人は時として、大きな賭けを避けようとする。やってみようとする前にはなからダメだと諦めてしまうのだ。しかし、一見不可能に思えることも、実はそれほど遠い夢ではないことも多い。熟慮と努力によって大胆なアイデアが実現できる」(『ディズニーCEOが実践する 10 の原則』ロバート・アイガー著、関美和訳、早川書房、2020年)
引用:『漫画村の真相 出過ぎた杭は打たれない』星野ロミ著
星野ロミ氏の言葉は、物議を醸しつつも、彼自身の経験と哲学に基づいた多角的な視点を提供しています。
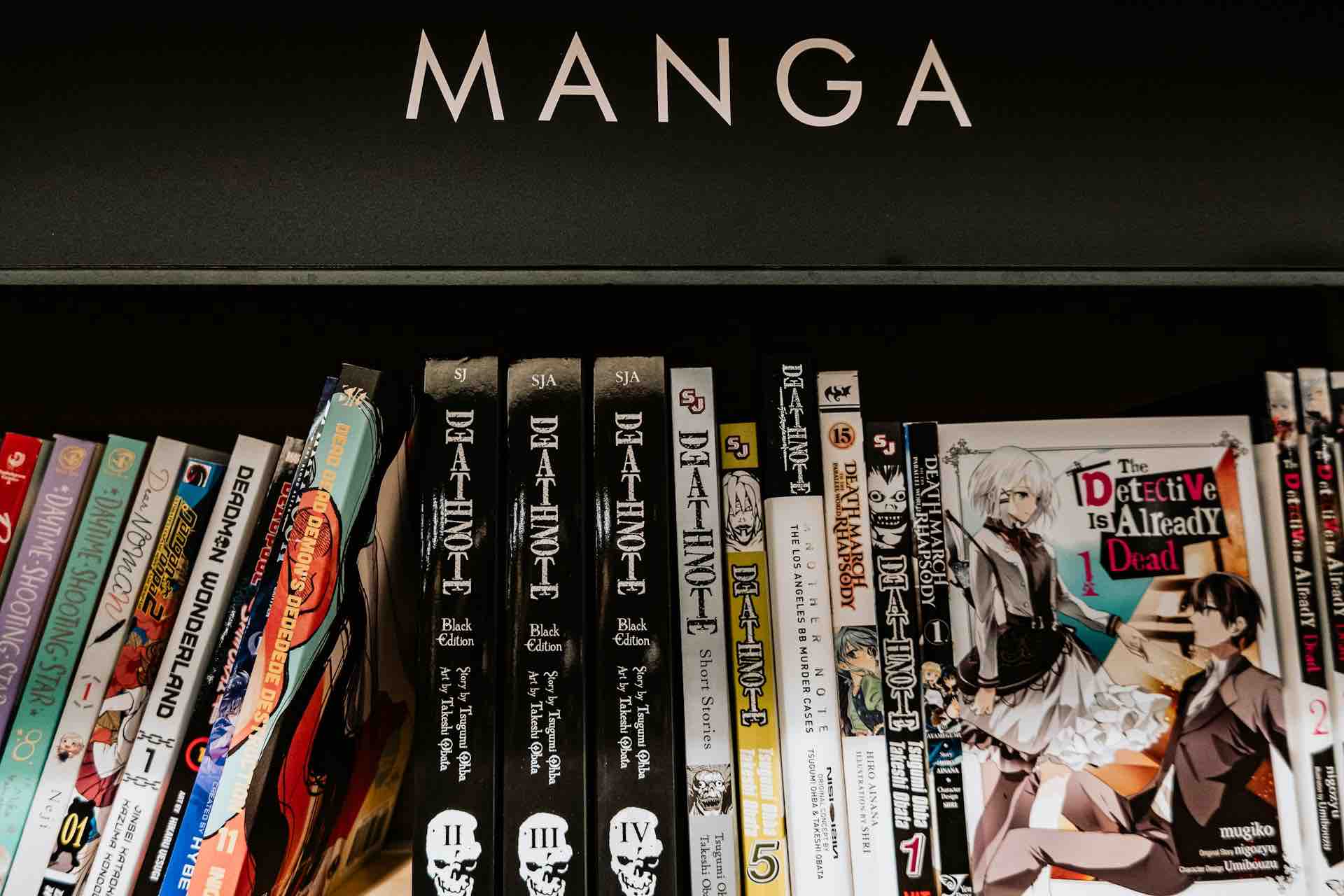
コメント