日々の生活で感じる「疲労」。仕事の忙しさや運動によるものだと考えがちですが、実はその背後にはもっと奥深いメカニズムが隠されています。近藤一博氏の著書『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』を参考に、私たちが感じる疲労の正体、そして「疲労感」と「疲労」の違いについて深く掘り下げていきましょう。
「疲労感」と「疲労」は違う?製薬会社のCMに隠された真実
私たちは日常的に「疲れた」と感じますが、この「疲労感」と、体内で実際に起こっている「疲労」は明確に区別されるべきだと、日本の多くの研究者は考えています。
テレビで栄養ドリンクの宣伝を見ていても、誠実な製薬会社のCMは、「疲労感 を減少させる」ときちんと言っています。「疲労を減少させる」と言うと、誇大広告になるということがわかっているからです。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
この言葉からもわかるように、私たちが感じている「疲労感」は、身体の本当の状態を必ずしも正確に反映しているわけではありません。では、「疲労感」とは一体何なのでしょうか?
すべての人や動物にまで共通する「疲労感という感覚」とは、いったい何なのでしょうか?その答えは、「休みたい」という気持ちです。難しい言い方では「休養の願望」といいます。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
疲労感とは、つまり「休みたい」という脳からのシグナルなのです。
生理的疲労のメカニズム:脳と炎症性サイトカイン
では、この「休みたい」という感覚はどのようにして生まれるのでしょうか。
まず結論からいいますと生理的疲労では、「疲れた」という感覚、すなわち「疲労感」は、脳の中で生じます。体内で産生された「炎症性サイトカイン」という物質が脳に入って、脳に働きかけることで生じるのです
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
体内で作られる炎症性サイトカインという物質が脳に作用することで、疲労感が生まれるというのです。さらに、この生理的疲労においては、「疲労感」と「疲労」は以下のように定義されます。
こうして、疲労によって細胞に負荷がかかると、ISRがこれに反応して細胞の動きを止め、代わりに炎症性サイトカインを産生し、この炎症性サイトカインが脳に伝わって疲労感をもたらすという生理的疲労のメカニズムが見えてきました。この知見をもとに、生理的疲労では「疲労感」と「疲労」の区別は次のようにまとめることができます。 疲労感……ISRによって産生された炎症性サイトカインが脳に伝わって生じる感覚 疲 労……ISRを引き起こす のリン酸化による細胞の停止や細胞死 疲労の原因はISRと呼ばれるストレス応答であり、それを引き起こすのがのリン酸化ということになるわけです。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
つまり、疲労感は炎症性サイトカインが脳に伝わることで生じる感覚であり、疲労とはストレス応答(ISR)によって細胞が停止したり細胞死が起きる身体の状態を指します。
徹夜で「元気」に感じるのは危険なサイン?
仕事の締め切りなどで徹夜を経験したことがある人もいるでしょう。「意外に元気だった」と感じるかもしれませんが、これは注意が必要です。
仕事の締め切り直前で徹夜をしなければならなくなったときは、HPA軸が強く働きます。このため疲労感は本来の量よりも減少します。一晩徹夜しても意外に元気、といった経験をされた方も多いのではないかと思います。しかしこの状態は、副腎皮質ホルモンとアドレナリンやノルアドレナリンによって「疲労感」が抑制されているだけなので、「疲労」、すなわち のリン酸化による細胞の障害は、どんどん蓄積されていきます。過労死、とくに心不全などの臓器障害で突然亡くなるタイプの過労死は、このような現象が原因と考えられます。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
この状態は、ホルモンによって疲労感が抑えられているだけで、細胞の障害は蓄積され続けている危険な状態なのです。過労死の背景には、このようなメカニズムが関係していると考えられています。
エナジードリンクと抗酸化剤の「落とし穴」
エナジードリンクや抗酸化剤についても、その効果のメカニズムは私たちが想像しているものとは少し異なるようです。
エナジードリンクの疲労感減少効果がカフェインによるものだというのは、ちょっと考えれば間違いだということがわかります。なぜなら、エナジードリンクに入っているカフェインの量はほとんどの場合、コーヒーに入っているカフェインの半分以下にすぎないにもかかわらず、エナジードリンクの疲労感減少効果は、コーヒーと比べると絶大だからです。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
カフェインの量だけでは説明できない、エナジードリンクの疲労感減少効果の背景には、別のメカニズムが働いている可能性があります。そして、抗酸化剤についても、注意が必要です。
抗酸化剤によって、疲労感のもとになる肝臓で産生される炎症性サイトカインが減少するため、脳は「疲れていない」と解釈し、体を休ませるシグナルを出さないことです。このため、無理に体の組織を使って過剰な リン酸化を生じさせてしまい、組織の障害や、ひいては突然死を招いてしまう可能性があるのです。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
疲労感の原因となる炎症性サイトカインを減らすことで、脳は「疲れていない」と誤解し、結果として身体に無理をさせてしまう可能性があるというのです。これは、疲労感を抑えることと、身体の疲労そのものを回復させることの重要性を物語っています。
疲労回復のカギ:運動とビタミンB1
では、本当に効果的な疲労回復方法とは何でしょうか。
軽い運動で疲労回復力アップ
意外に思えるかもしれませんが、軽い運動は疲労回復に効果的です。
軽い運動をしたグループでは、疲労回復指数が上昇していました。これは、軽い運動によって適度な生理的疲労がもたらされたことにより、疲労回復力が増強されたためであると考えられます(図1‐11)。つまり、軽い運動は疲労感を減少させるのではなく、疲労回復力を高めることで生理的疲労そのものを減少させるのです。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
軽い運動は、疲労感を直接減らすのではなく、疲労回復力を高めることで生理的疲労そのものを減少させる効果があるのです。
疲労回復に不可欠なビタミンB1
ビタミンB1も疲労回復において重要な役割を果たします。
ビタミン が多くのビタミン剤や栄養ドリンクに疲労回復効果をうたって配合されていることも、ご存じの方は多いかと思います。ビタミン というよりも「アリナミン」と言ったほうがピンとくるかもしれません。あの有名な製品は、吸収力を高めたビタミン のことなのです。 われわれはこのビタミン に、本当に疲労回復効果があるのかどうか、調べてみました。 ビタミンは通常、不足していることが問題となるので、ビタミン を含まない食事をマウスに4週間与えて、疲労回復指数がどのようになるかを観察しました。 その結果、ビタミン 不足の状態が4週間続いたことによって、マウスの疲労回復指数は著しく減少したのです(図1‐12)。これにより、ビタミン が不足すると、疲労回復力が大きく低下することがわかりました。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
飲酒によってビタミン は体内で大量に消費されてしまうので、飲酒量が多い人はビタミン 不足になりやすいことがわかっています。日本人の約3分の1がビタミン 不足であるという報告もあります。 製薬会社の片棒を担ぐつもりはないのですが、ビタミン が不足すると本当に疲労回復力を低下させてしまうので、継続的に摂取することを心がけたほうがよいと思います。 ちなみに、日本人のビタミン 不足が近年は改善されてきたのは、ビタミン剤が開発されたことに負うところが大きいといわれています。それほどまでに、白米を食べるようになった日本人はビタミン 不足だったのです。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
ビタミンB1は、疲労回復力を高めるために不可欠な栄養素であり、不足すると疲労回復力が大きく低下してしまいます。特に飲酒量の多い人や、白米を主食とする日本人には不足しがちであると指摘されています。
病的疲労の正体:うつ病と新型コロナ後遺症
疲労は単なる身体の疲れだけではありません。近藤氏の著書では、病的疲労についても詳しく解説されており、特にうつ病や新型コロナ後遺症との関連が示唆されています。
●うつ病は病的疲労であり、主な症状の一つは疲労感である。それは脳内炎症によって生じる。
●うつ病の原因は、脳内炎症説が最有力とみられる。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
●新型コロナ後遺症は脳の炎症が原因と考えられる。
●新型コロナウイルスはヒトの脳では増殖しない。
●新型コロナ後遺症は慢性疲労症候群によく似ている。そのため、原因ウイルスが不明という慢性疲労症候群の問題を解決する突破口となる可能性がある。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
病的疲労としてのうつ病や新型コロナ後遺症の背景には、脳内炎症が深く関わっていると考えられています。興味深いことに、新型コロナ後遺症の原因が、これまで原因不明とされてきた慢性疲労症候群の解明につながる可能性も示唆されています。
疲労の原因は炎症性サイトカイン
生理的疲労と病的疲労、どちらも共通する疲労感の原因が指摘されています。
①疲労感の原因は、脳が炎症性サイトカインにさらされることである(これは生理的疲労も病的疲労も同じ)
②脳が炎症性サイトカインにさらされる原因は、次のとおりである 生理的疲労……末梢組織で産生される炎症性サイトカイン 病的疲労……脳内の炎症
③新型コロナ後遺症の脳内炎症の原因は、脳のコリン作動性抗炎症経路の障害である
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
つまり、「疲れた」と感じる原因は、生理的なものであれ病的なものであれ、脳が炎症性サイトカインにさらされることにあるというのです。そして、その炎症性サイトカインがどこで産生されるかが、生理的疲労と病的疲労の違いを生み出します。
生理的疲労と病的疲労を分けるもの
最終的に、生理的疲労と病的疲労を分けるものは何か、そしてどのように移行するのかについて、重要な示唆が与えられています。
●生理的疲労と病的疲労を分けるものは脳内炎症が起こっているか否かであり、その違いを生むのはコリン作動性抗炎症のしくみが正常に働いているかどうかである。
●生理的疲労が過度に強くなると、病的疲労に移行することがある。自分がどちらの疲労かは、唾液中のHHV‐6を測定すればわかる。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
脳内炎症が起きているかどうかが、生理的疲労と病的疲労の分かれ目となります。そして、生理的疲労が極端に強くなると、病的疲労へと移行する可能性も指摘されています。
疲労との付き合い方
著書では、疲労そのものをなくすことの危険性も指摘されています。
●疲労そのものをなくそうとすることは危険である。SITH‐1や、うつをなくそうとすることも得策ではない。
●人類は疲労やうつとうまくつきあっていくしかない。
引用:『疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた』近藤一博著
疲労は、私たちの身体が発する大切なサイン。そのサインに耳を傾け、適切な対処をすることが、健康を維持するために不可欠だと言えるでしょう。日々の疲れを感じたら、それが単なる疲労感なのか、それとも身体が発しているより深刻なサインなのか、一度立ち止まって考えてみる良い機会になるかもしれません。
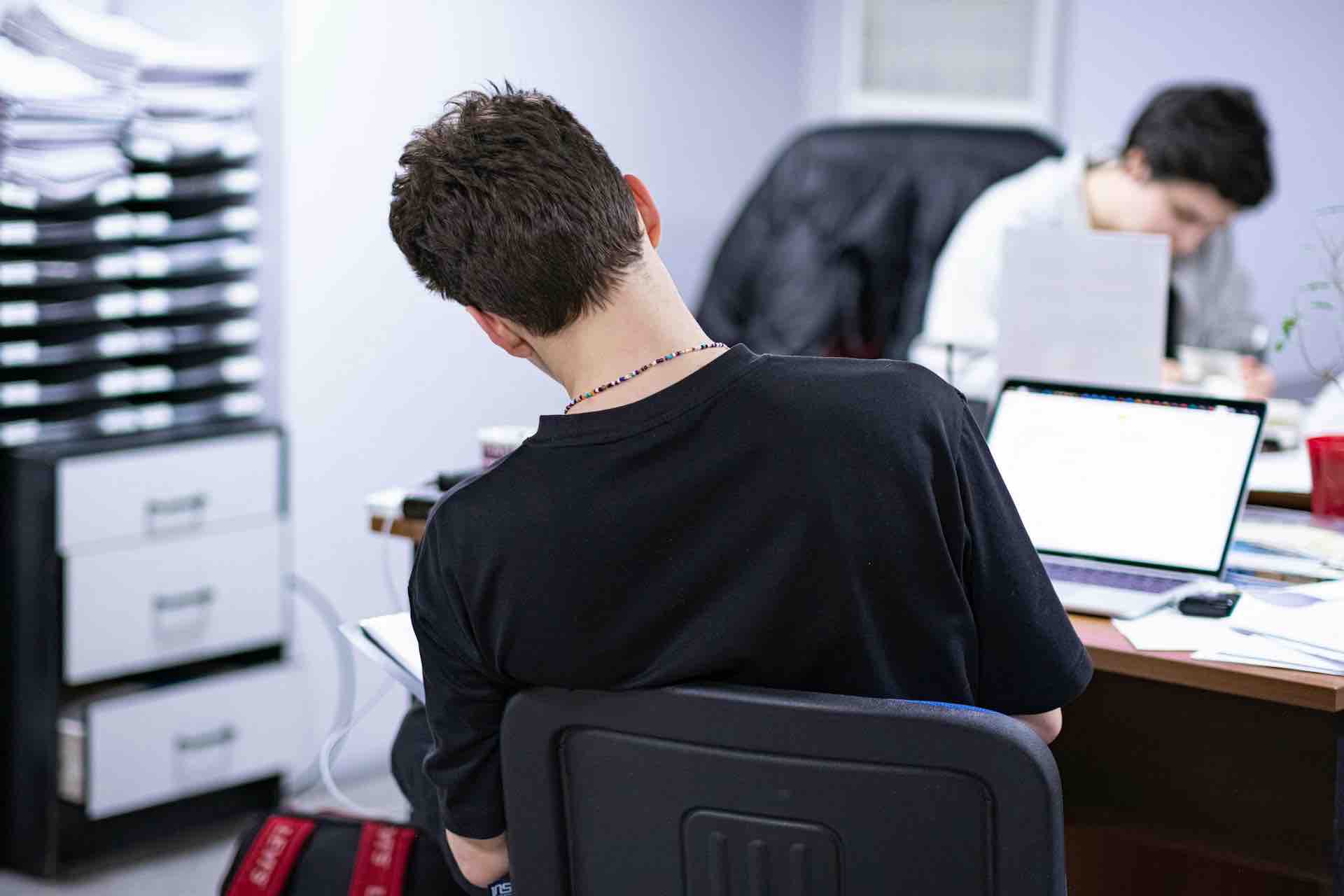
コメント