仕事で成果を出し続けるトップ5%の社員は、多忙な日々の中でも読書を習慣にしています。彼らがどのようにして読書時間を確保し、その知識を成果につなげているのか。AI分析で明らかになった、効率的で効果的な読書術をまとめました。
読書時間を生み出すには「何かをやめる」こと
多忙なトップ5%社員が読書時間を確保できるのは、単純に時間管理がうまいからではありません。彼らは何かを「やめる」選択をすることで、読書時間を捻出しています。
「誰しも1日は 24 時間。突出した成果を出したからといって時間がもらえるわけではありません。同じ 24 時間の中で読書を習慣にできたということは、 他の人よりも『何かをしない』選択をしている のです。」
引用:『AI分析でわかったトップ5%社員の読書術』 越川慎司著
テレビやSNS、スマホをいじる時間、休日の買い物など、日常生活に潜む「やめる」べき習慣を見つけ出し、その時間を読書に充てているのです。こうした小さな変化の積み重ねが、やがて大きな習慣の変化につながっていきます。
効率と達成感を高める読書術
トップ5%社員は、ただ闇雲に本を読むわけではありません。効率的に知識を吸収し、読書を継続するための工夫を凝らしています。
1. 「耳で読む」オーディオブック
トップ5%社員の64.2%がオーディオブックの利用経験があるのに対し、一般のビジネスパーソンはわずか0.8%にとどまります。この圧倒的な差は、効率的に知識を吸収しようとする彼らの意識の高さを物語っています。さらに、彼らの多くは「1.5倍速」でオーディオブックを聴いています。これはただ時間を短縮するためだけでなく、記憶の定着率を高める効果も期待できる、科学的にも裏付けられた方法です。
2. 本は「立てて」保管する
本棚に本を積んでしまい、いつの間にか「積ん読」状態になっている人も多いのではないでしょうか。AI分析の結果、本を「横積み」で保管しているグループの未読率が1年後に75%だったのに対し、「立てかけ」グループは47%まで下がったことがわかりました。 「立てかけ方式を採用することで、積読を約 28%も減らすことができた のです。」
引用:『AI分析でわかったトップ5%社員の読書術』 越川慎司著
本を立てて置くだけで、未読率が大幅に下がるというシンプルな方法ですが、効果は絶大です。
3. まずは「薄い本」から始める
新年や新年度など、読書習慣を始めようと意気込む時期ほど、分厚い本に挑戦しがちです。しかし、トップ5%社員は逆のアプローチを取ります。
「薄い本から読み始めることで、読了感と達成感を得やすく、習慣化のハードルを下げることにつながります。」
引用:『AI分析でわかったトップ5%社員の読書術』 越川慎司著
短時間で確実に読み終えることで得られる達成感は、「自分にもできた!」という自己効力感につながり、読書を継続する大きな原動力となります。
知識を「血肉」にする読書術
ただ本を読むだけでは、得た知識は一時的なものになってしまいがちです。トップ5%社員は、読んだ知識を自分自身のものにするためのアウトプットを重視しています。
1. 読後10分以内のアウトプット
トップ5%社員の87%が、本を読み終えた後10分以内に何かしらのアウトプットをしています。メモを取る、SNSに投稿する、誰かに話すなど、形式は問いません。このアウトプットの目的は、読んだ内容を「自分ごと化」すること。得た知識を自分の考えや行動に結びつけることで、知識を「一次情報」へと昇華させています。
2. 色分け付箋とアクション管理
付箋の活用法にも違いが見られました。トップ5%社員は、付箋をただ貼るだけでなく、色分けを徹底したり、番号を振ったりしています。たとえば、「R」は再読すべき重要ポイント、「A」は実践したいアクション、といったように目的別に分類することで、後から見返したときに内容を素早く理解できるように工夫しています。
3. 複数の媒体とジャンルを使い分ける
彼らは紙の本、電子書籍、オーディオブックを使い分け、読書の効率を最大化しています。また、ビジネス書だけでなく、歴史、科学、哲学、文学など、幅広いジャンルの本を読むことで、知識の幅を広げ、創造性を高めています。
読書環境にもこだわる
読書の成果は、読む内容だけでなく、読む環境によっても大きく左右されます。トップ5%社員は、集中力を高める環境づくりにも気を配っています。
1. 喫茶店を「秘密基地」にする
トップ5%社員は、自宅以外で読書する比率が特に高く、喫茶店での読書は一般社員の1.9倍にもなります。地元の小規模な喫茶店は、日常の喧騒から離れ、読書に没頭するための「第三の場所」として機能しているのです。
2. 照明の明るさに注意する
明るすぎる照明環境(1000ルクス以上)は、眼精疲労を増やし、集中力を低下させることが科学的に証明されています。トップ5%社員は、適度な明るさ(300~750ルクス)の照明環境を選んで読書に臨んでいます。
読書を習慣にする「ジジジの法則」
読書を習慣化するための具体的なステップとして「ジジジの法則」があります。
-
時間(ジカン)の可視化: 自分が何に時間を使っているかを把握し、スキマ時間を見つける。
-
準備(ジュンビ): スキマ時間に備え、電子書籍やオーディオブックをすぐに使える状態にしておく。
-
自己(ジコ)効力感の獲得: スキマ時間を活用できたら、自分を褒めて「自分にもできた!」と認識する。
この3つのステップを繰り返すことで、読書は無理なく継続できる習慣へと変わっていきます。
あなたも今日から、これらの読書術を試してみてはいかがでしょうか。
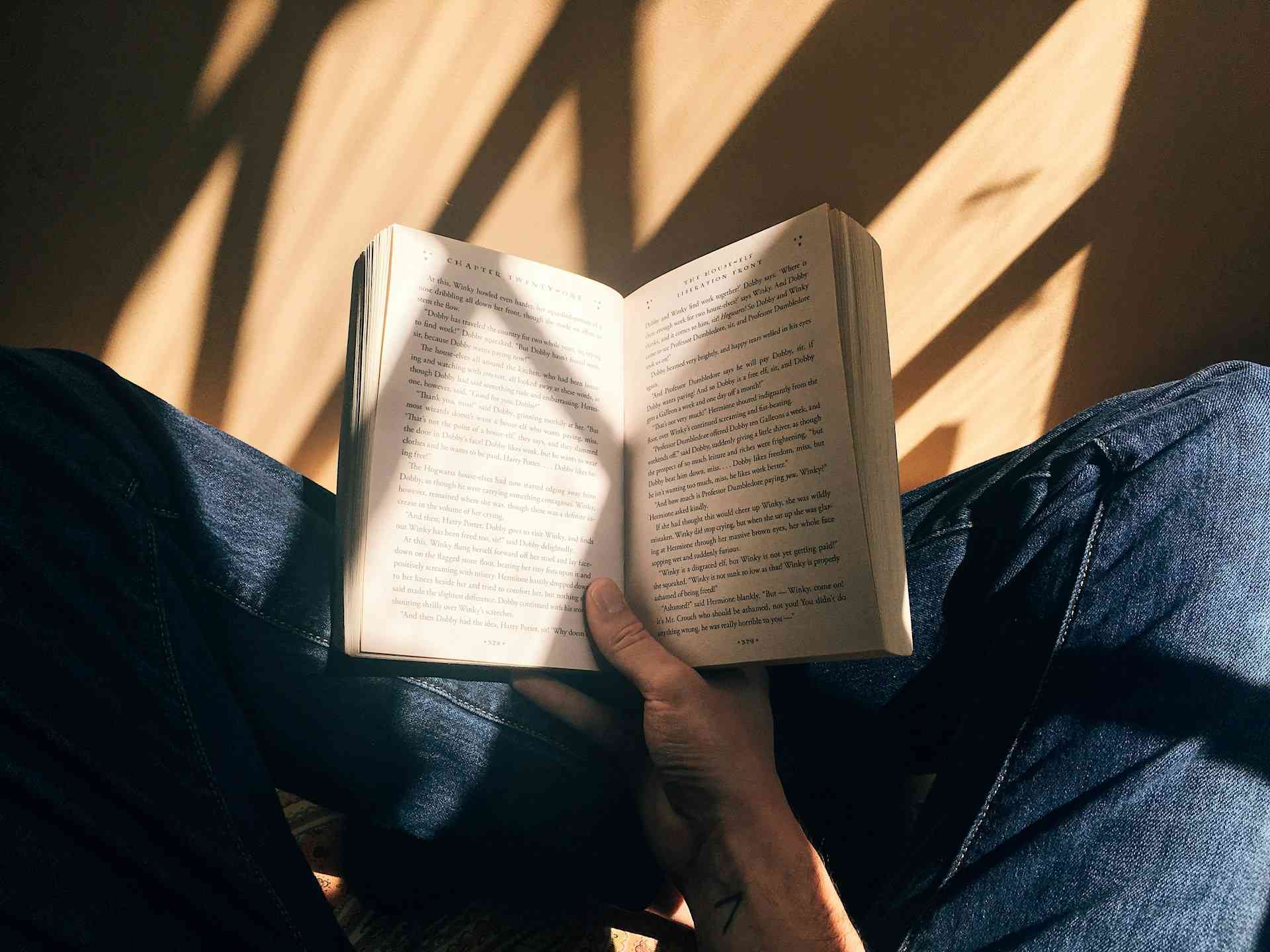
コメント